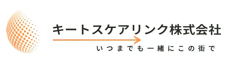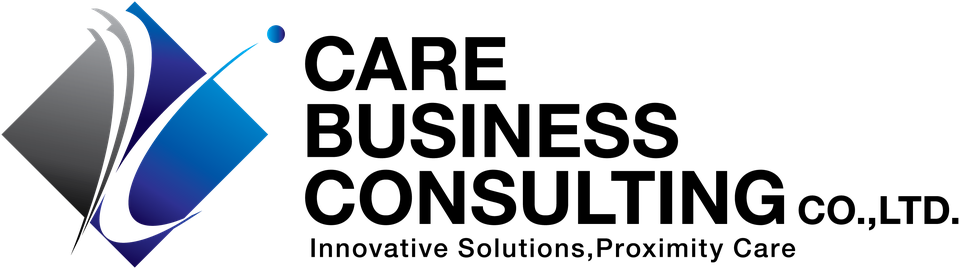私たちの訪問介護事業の考え方
キートス・ケアサービスは、単なる訪問介護事業所ではありません。
これからの時代に求められる「訪問介護事業者の在り方」を模索し、その姿を実現していくことを使命としています。
-
模範的な存在として
訪問介護事業者としての模範となり、運営の実態を積極的に開示することで、他の事業者の手本となることを目指します。 -
実験的な取り組み
「あるべき運営方法や手段」を固定化せず、常にイノベーションに挑戦する実験的な事業所として位置づけています。 -
スモールオフィス・ドミナント戦略
新規参入事業者の参考事例となるために、一定の売上規模を維持しながら、多事業所展開を進めています。
小規模で地域密着型の事業所を複数展開し、地域に深く根差したサービスを広げます。 -
あらゆる角度からの運営
経営・人材・ICT活用・地域連携など、あらゆる角度から事業運営に取り組むことで、訪問介護の未来を切り拓く参考事例となることを目指しています。
私たちが目指すもの
「死ぬってどんな気分なんだろう」
そんなことをふと考えてしまうことは誰しもあると思います。
それは別にネガティブな気分に限ることなく私たちがこの世に生きている以上、逃れることの出来ない究極の想像です。
「訪問介護」という仕事に向き合っていると、
そういう“究極の想像”から目をそらせなくなる時があります。
目の前にいる利用者さんの人生を考えます。
その人の時間の重みや、心の声に触れようとするとき、私たちは健常であり、そもそも「その人ではない」という事実。
わかっているつもりで、わかっていないこと。
わかりたいと思いながら、たどり着けないこと。
それでも、わかろうとし続ける姿勢だけが、きっと“寄り添う”ということの本質なんだと思います。
わたしたちキートス・ケアサービスが大切にしている言葉があります。
それは「まなざし」です。
助ける・助けられるという構図ではなく、
ともに“今を生きる”という姿勢で、
わからない痛みや思いに、誠実に向き合い続けるまなざしです。
2025年時点で日本の全65歳以上約3,590万人中、約717万人が介護認定を受け、その割合は約20%=5人に1人 が介護を必要としています。さらに、日本には960万人(人口の約7.6%)もの障害をお持ちの方がいます。前提としてその数は「障害者手帳の発行数」です。
よく2022年度の介護職員の数は約215万人で2026年には約240万人が必要で約25万人の不足見込み 。さらに2040年には約57万人の不足が予測される などと聞きます。
その数字を語られる度、いつも私は違和感を感じてしまいます。
行政は「人数確保・制度整備重視」に傾きがちな一方、現場は、「時間をかけて相手を理解すること」の重要性や、「寄り添うケアの質」が軽視されかねない制度設計への憂慮があります。
その両方の視点に現行制度と現場との大きな溝を感じます。
これからの介護に必要なのは、制度や効率を超えて、一人ひとりの“生き方”を尊重できるケアのかたちなのだと思いたい。
その人が「どう生きたいのか」に対して、
私たちが「どう在るのか」を問われる時代が、もう来ていると思います。
きれいごとじゃなく、泥臭くても、本気で向き合っていきたい。
それこそが、私たちがこの仕事を選んだ意味だし、キートス・ケアサービスが目指すケアの姿です。
キートスケアリンク株式会社
〒194-0022
東京都町田市森野二丁目25-9
東海町田マンション101
TEL : 042-854-7781
FAX:042-810-4763
E-mail: info@kiitos-tokyo.co.jp